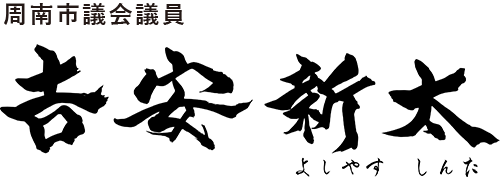目次
1.不登校対策について
- 文部科学省が策定したCOCOLOプランにおいて、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」とあるが、本市ではどういう取組をしてきたのか
𠮷安)これまでもこの場で不登校について多く取り上げられてきました。子供は学校に行きたいのに行くことができない。保護者としては学校に行ってほしい。今学校に行けないことが子供にとっての将来を大きく左右する可能性があるから、だからこそ、当事者の子供も大人も大変苦しい思いをしている。それがいわゆる不登校問題の根底にあると認識しています。今回は私なりの視点で質問させていただきます。答弁には過去と重なるところもあるかと思いますが、再確認の意味も含めてよろしくお願いします。
義務教育とは、小学校と中学校において国と保護者が子供に普通教育を受けさせる義務を負う制度です。
不登校とは、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因により、児童生徒が学校に登校しない、または登校したくてもできない状況にある状態のことです。病気や経済的な理由を除く、年間30日以上欠席した児童生徒がこれに該当するとあります。
義務教育、不登校を辞書で引くとこう書かれています。それを踏まえてこれをここに置き換えますと、周南市と各家庭が一緒になって子供を学校に通わせる努力をしましょうと捉えます。学校に当たり前に通うことができて初めて義務を果たすと解釈します。
学校が楽しくて楽しくて毎日るんるんで行く子もそれはいるでしょう。ですが、我々大人が社会的責任のため、家族を養うため、生活していくために気持ちが乗らない日もあるが、毎日会社や職場に通い働くのと同じで、子供も平日朝が来れば支度をし、嫌々言いながらも通っている子も一定数いると思います。それは学校には通うものだよと家庭でもしつけていますし、学校でもそう教えていただいているから、子供も行くべきという意識が働いているものと考えます。
私は、幼稚園のとき、絵の具の時間の後に洗い場で色水を頭にかけられるのが嫌で嫌で何度も泣きながら行きたくないとじらを言っていたのを幼心に覚えていますが、40年も前の話です。当時は、母親に髪を引っ張られるようにして無理やり登園していました。幼稚園と義務教育は同じにはできませんが、行きたくない子供の気持ちはとても分かります。
実体験を基にする上では言わなければなりませんが、小学生のときは今度はいじめの加害者側になってしまいました。謝っても謝っても消える過去ではありませんが、いじめに関しては加害者も被害者も経験して今に至っています。
現在まで2人の子を持つ親となり、息子は中学2、3年と起立性調節障害にかかり学校に通えなくなりました。本人はもちろん苦しかったことでしょう。同じように我々夫婦、また同居している娘、祖母、曽祖母も彼と一緒に苦労を共にしました。不登校の子を持つ親の気持ちも分かりました。
下の娘は今小学校に通っていますが、今日学校へ行きたくないという日がたまにあります。「何言っちょるんかね、絶対に行きなさい。」とは言いません。「そうか、今日は休む。」と聞きます。そういったやり取りをした結果、時間になるとありがたいことに毎日通うことができています。
昭和から平成を経て令和の現代、社会問題とまでなってしまった不登校、子供の主体性を重んじること、我々親世代がいわゆるスパルタ教育ではないことも数が増加している要因の一つなのかも分かりません。
今現在、本市やお隣の下松市には不登校のお子さんをお持ちの主にお母さんが、家庭でも学校でもない第三の居場所をつくり、子供のことを一番に考えていろいろと活動されています。私も子育て現役世代の者として、また、同じ当事者としての立場で自分にできることはないかと日々考えています。
第三の居場所には積極的に参加して、実際に悩まれる声を聞き、自分の中に落とし込んで寄り添っているつもりでいます。私一人にできることは知れていますが、こうして取り上げることで、ここにおられる皆様や市民の皆様と情報を共有して課題解決に向けてできることを1つずつ進めていきたいと思います。
以上を踏まえて、(1)文部科学省が策定したCOCOLOプランにおいて「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」とあるが、本市ではこれを踏まえてどういう取組をしてきたのかお尋ねします。
答)それでは、文部科学省が策定したCOCOLOプランにおける、本市での取組についての御質問にお答えいたします。
近年、不登校児童生徒数は増加傾向にあり、議員がおっしゃられましたように、生徒指導上の喫緊の課題となっております。
こうした状況を受けて、文部科学省は、令和5年3月、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、いわゆるCOCOLOプランを策定いたしました。
このCOCOLOプランには、3点の指針が示されております。
1点目は不登校児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整える。2点目は心の小さなSOSを見逃さず、チーム学校で支援する。3点目は学校の風土の見える化を通して、学校をみんなが安心して学べる場所にする、の3点でございます。
このCOCOLOプランで示されました、それぞれの指針における本市の取組について御説明をいたします。
まず、1点目の不登校児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整えるについてです。
本市では、教育支援センターを設置し、指導員による学習支援やスクールカウンセラーによる教育相談等を行うなど、個々の状況に応じたきめ細かな支援を行っております。
さらに、山口県教育委員会が、令和5年度から始めた不登校対策事業により、本市で、太華中学校、住吉中学校、富田中学校、熊毛中学校の4中学校に校内教育支援センター、通称ステップアップルームが設置され、専属教員が不登校等生徒の学習支援や教育相談などに取り組んでおります。
また、学校においては、在籍学級で授業を受けることが難しい児童生徒のために別室を準備し、1人1台端末を活用して、オンライン授業や学習eポータルを受けることができる体制を整えております。
次に、2点目の心の小さなSOSを見逃さず、チーム学校で支援するについてでございます。
本市の各学校では、不登校の未然防止や兆候の早期発見のために、授業態度や出席状況、表情、言動などを日々観察するとともに、週1回の生活アンケートや定期的な個別面談、教職員間での情報共有などを行っております。
さらに、必要に応じて関係教職員でケース会議を開催し、具体的な取組について協議をしております。
その協議の際、学校だけでは解決が難しい課題が見られた場合は、福祉、医療、警察等の専門機関と連携して、情報の共有や必要な支援についての協議を行っております。その中でも、医療面での支援が必要と思われるケースについては、専門家の助言を踏まえて家庭と医療の橋渡しを担う場合もございます。
最後に、3点目の学校の風土の見える化を通して、学校をみんなが安心して学べる場所にするについてです。
文部科学省が策定したCOCOLOプランによりますと、学校の風土の見える化とは、学校評価の仕組みを活用して、児童生徒の授業への満足度や教職員への信頼感、学校生活への安心感などの学校の風土や雰囲気を把握し、学校運営を改善することが示されております。本市の各学校では、学校の教育目標や学校評価の結果をホームページに公開したり、学校運営協議会の場で取組を紹介したりしております。
また、学校をみんなが安心して学べる場所にするために、学校で過ごす時間が最も長い授業において、児童生徒一人一人が考えを持ち、意見交換をしたり、1人1台端末を活用して興味・関心等に応じた学習を行ったりするなど、日々の授業改善にも取り組んでおります。
さらには、社会の変化を踏まえた校則の見直しや学校運営協議会に児童生徒が参加し、地域の方と地域課題について話し合う熟議を行うなど、児童生徒が主体的に参加できる場を設けるよう努めているところでございます。
教育委員会といたしましては、引き続き、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策に努めてまいります。
𠮷安)ステップアップルーム、初めて聞きました。ありがとうございます。何点か再質問させていただきます。
COCOLOプランの中に不登校特認校の推進とあると思います。ですが、本市には現状整備はされていないかと思います。近いものでいうと、小規模特認校はあります。保護者の送迎の負担という大きな問題はありますが、市内であれば、校区を飛び越えて通うことができる小学校です。
自分の校区では通えませんでしたが、この制度を使い、小学校に通えるようになったというお母さん方から、何人かからお話を聞く機会がありました。中には、西部から東部の端から端まで毎日送迎していたという御苦労も聞かせていただきました。そのときは、令和4年度でした。鼓南と八代、和田、須磨小でありました。
令和6年に三丘小が加わり、今年度から鹿野小も追加されました。当時は、西部と南部と東部だけなんだなという個人的な認識でしたのですが、北部、中心部にも小規模特認校があれば児童と保護者の方の選択肢も広がるし、何より送迎の負担が減ると考えていました。
今現在、市内中心部には小規模特認校がありませんので、近年、児童数が減少している、周陽、秋月小のどちらかで、今後、ぜひ御検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
答)今お話がありました小規模特認校というのは、小規模な学校における教育活動のより一層の活性化を図ることを目的としておりまして、学校の状況としては、欠学年、例えば2年生に児童がいない、3年生にもいないとか、そういう欠学年がある学校、あるいは複式学級を有する学校、いずれも小学校ですけども、そのうち、児童の豊かな人間性の育成を図るとともに、少人数を生かした特色ある教育活動を展開している小学校というふうに本市では定めておりますので、今言われた学校がそれに該当するということで、さらに各学校の学校運営協議会でしっかり協議をされて、合意を図った上で教育委員会に申請が来るという手順を踏めば可能かと思いますけれども、そうでない学校については、申し訳ありませんが該当しないということで御理解いただけたらと思います。
𠮷安)小規模特認校に見学に行った際に、担当された先生から、ここは不登校児童を受け入れる場所ではないと言われたと聞きました。子供の通いたい、学びたい、保護者の通わせたい気持ちは最大限尊重すべき事案だと考えます。
小規模特認校を不登校特例校も兼ねる制度の整備を提案いたします。これは不登校児童を一人でも救うことに大きくつながるものであると信じます。教育長の御見解をお聞かせください。
答)小規模特認校につきましては、先ほど申しましたように、小規模の学校における教育活動のより一層の活性化を図るということを目的としております。その中で、保護者がその学校のそういった教育活動に賛同して、様々な御理解を頂いた上で通うということを前提条件にしております。
一方、不登校特例校、今、学びの多様化学校というふうに呼ばれるんですけれども、こちらについては、不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程というものを編成をして教育を実施する必要があると認められる場合に、文部科学大臣が学校として不登校の特例校、学びの多様化学校にするということになっておりますので、この2つの制度につきましては、制度、目的が全く異なりますので、現在の本市の小規模特認校の趣旨を踏まえた取組というのは、現状のままで進めていきたいというふうに思います。
𠮷安)COCOLOプランに教育支援センターの拡充とあります。本市には楠木にあります。ここは、不登校傾向にある中学生に当たる生徒が通う施設と認識しています。
手元に施設のしおりを持っていますが、とても生徒と保護者に寄り添った内容が書かれています。ですが、実際に利用したことがある関係者の方から、又聞きなので正確ではないかもしれませんが、ここでは実際に通うべき学校と同じカリキュラムに基づいて教えることが前提であり、生徒が学びたい箇所やつまずいている箇所を補習する場ではないと聞きました。実際の施設での過ごし方の現状をお聞かせください。
答)今、議員、中学生と言われたかと思いますけども、小学生も対象としておりますので、小中学生ということで御理解いただけたらと思います。
教育支援センターにつきましては、スタッフとして教員経験者、養護教諭経験者、臨床心理士などを配置しております。学習支援や心理的支援、家庭支援、さらには保護者や学校からの相談ということの対応を行っているところでございます。
また、環境としては、子供たちの在籍校とつないだオンライン指導や授業配信が受けられるよう、ICTの環境も整備をしているところでございます。
そうした中で、通室する児童生徒は、自分でその日の学習内容や教科を決めて取り組んでおります。例えば、体調や前日の学習状況に応じまして、今日は理科のプリントから始めたいとか、作文を書きたいとかということで、自ら計画を立てて学習に向かっております。
指導員は、その時々の子供たちの様子を丁寧に観察しながら、声かけをしながら学習を促しているという状況でございます。
それから、午後が中心になるんですけれども、通室している児童生徒の自主性を高めるために、自分たちで計画したふれあい活動というものも実施しております。バレーボールとか体操、モルックなどを通じた交流であったり、サツマイモなどを植える体験であったり、スクールカウンセラーが行いますソーシャルスキルトレーニングのようなものも実施して、多様な活動を通して公共心あるいはコミュニケーション能力を育んで、社会的自立に向けた支援につなげているところでございます。
𠮷安)本市の教育支援センターが、小中学生が対象というのを初めて知りました。教えていただいてありがとうございました。
私が昨年、この施設を訪れた際は、教員の資格を持った方が常駐ではないとは思いますが8名であり、その日に授業を受けていた方は1人でした。その方は自分で通学しているとのことでした。すみません、中学生が限定だと思っていたので。
市内に現在、不登校生徒がこれだけ多くいるのに対して、時代と現場のニーズに合っていないのではと疑問を感じています。楠木という市内中心部だけではなく、東部、北部、西部、南部にもそれぞれ必要なのではないか。生徒が自分で通える範囲内に学べる環境を整えるべきではないか。施設を新たに造るのではなく、8名おられるのであれば、その先生方が各地区の小学校に赴いて空いている教室等を利用するなど、工夫をしていく段階に来ているのではないでしょうかと考えますが、今後の在り方について、教育長の御見解をお聞かせください。
答)先ほど8人と言われたんですけども、今、センターのほうで勤務していただいている職員につきましては、学校の教員上がりの先生が、元教員が3名、養護教諭が1名、それからスクールカウンセラーが1名、補助員が1名という状況でございます。
今後のことにつきましては、現状、センターに通ってもらって、そこで先ほど申し上げましたような取組をしながら、学校とつないでいくような形の取組を継続はしてまいりますが、前回の議会のときにもちょっと申し上げましたけれども、外に出向いていくということはできないだろうかということで、今、どういうふうにすればうまくいくのかということも検討をしているところでございます。
𠮷安)令和5年度第2回周南市総合教育会議のデータを基に、不登校の児童生徒の人数です。令和4年度の数字にはなりますが、小学生6,591人中78人、中学生3,417人中174人。総数1万8人中252人であり、全数に対しての不登校児童生徒の人数の割合は2.5%になります。
私が実際に不登校児童生徒の保護者の方から聞くには、どうもこの数字に若干の疑問を感じます。
学校によって呼び方は違うかも分かりませんが、本来通うべき教室に通えない生徒が入れる心の教室というものが市内にはあると思います。ここに通う生徒や、教室に行けずとも保健室に来た児童生徒は登校したとカウントされていると聞きました。また、学校の昇降口までは行けるんだが帰ってしまう。また、週に1日だけの登校であったり、1時間しか授業に参加できない日が続いていても、年間30日以上の欠席という定義に当てはまらなければ、保護者のほうが幾ら我が子が不登校傾向にあると認識していても、学校側は不登校児童生徒とはカウントしていないのではないかとの疑問をお聞きしました。ここは改めて確認しておきたいと思います。いかがでしょうか。
答)先ほど議員がおっしゃられました令和4年度の小学校が78人、中学校が174人という数字は、各学校のほうで年間30日以上の長期欠席の児童生徒の数が一応線が引かれておりまして、そちらのほうを文部科学省のほうに報告することになっておりますので、そういった対象となっているというふうに御認識いただけたらというふうに思います。
なお、今おっしゃられましたように、一日丸々学校にいるという状況ではなくて、何時間かとかいうような状況の子がいることはもちろん確かでございます。そういった子供たちの出欠については出席扱いになっていることが多いんじゃないかと思いますけども、そういった子供たちが30日を超えないけれども、今のように保護者の方も本人も苦しい状況になっているというのは確かに現実的にはあるというふうに思いますし、私も以前勤めた学校でもそういう子供たちはおりましたので、そういう子供たちに対する対応というのも当然必要になってくるというふうに思っております。
𠮷安)ありがとうございます。次に移ります。
- 周南市こどもまんなか宣言の中に「こどもが誰一人取り残されることなく」とあるが、不登校児のいる家庭では、「取り残されている」と感じていると聞く。取り残さないための不登校対策として、具体的な取組は
𠮷安)(2)全国に先駆けて周南市こどもまんなか宣言の中に「こどもが誰一人取り残されることなく」とあります。不登校児童生徒のいる御家庭では「取り残されている」と感じているとお聞きします。取り残されないための不登校対策として具体的な取組はどのようなことをされていたのかをお聞かせください。(1)の不登校対策とも重なるところがあると思いますが、御答弁よろしくお願いします。
答)それでは、こどもを誰一人取り残さないための不登校対策の具体的な取組についてお答えいたします。
本市では、令和5年5月にこどもが誰一人取り残されることなく、健やかに成長し、様々な学びや遊び、体験などを通して生き抜く力を育み、未来の町の担い手として活躍するという願いを込めて周南市こどもまんなか宣言を発表し、子供を真ん中に据えたまちづくりを進めております。
教育委員会では、このこどもまんなか宣言も踏まえながら、未来を生き抜くこどものための興味・楽しさ・勇気を育むこどもまんなか教育を基本理念とした第3期周南市教育大綱を令和6年度に策定いたしました。この大綱においては、きめ細かな支援体制の充実を推進方向の一つに掲げており、不登校や不登校傾向のある児童生徒一人一人の社会的自立に向け、適切な支援を行うこととしております。
学校現場では、不登校の未然防止に向けて、児童生徒一人一人が安心して学校生活を送れるよう、教職員による日々の声かけや教育相談、生活ノートなどを活用し、信頼関係の構築と早期対応に努めてまいりました。また、授業ではペア学習やグループ活動を取り入れ、児童生徒同士のつながりを深めるとともに、学校行事では、子供たちが主体的に関わることで、自己有用感や所属意識を育む工夫も行っております。
児童生徒に欠席が見られる場合には、速やかに家庭との連絡や家庭訪問を行い、3日以上の欠席が続く場合には、学校内でケース会議を開催するなど、組織的に対応しているところでございます。また、不登校の問題においては、子供自身だけでなく、保護者も孤立感や不安を抱えておられることがあり、こうした保護者に対する支援も重要と捉えております。
学校では、本人との教育相談や保護者への電話連絡、家庭訪問などを行い、家庭と連携しながら不登校対策に取り組んでいますが、学校だけでは解決が難しい課題が見られた場合には、必要に応じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家を含めて情報を共有し、必要に応じて関係機関と連携した支援に取り組んでいるところでございます。
今後も、学校や関係機関と連携し、誰一人取り残されることのない教育の実現に向けて、きめ細かな取組を継続してまいります。
𠮷安)学校教育でのお立場での取組は大変よく分かりました。今後も引き続きよろしくお願いいたします。次に移ります。
- 中学校部活動の地域移行によって、部活動を受け持っていた教職員は放課後に時間ができる。不登校傾向のある児童生徒への寄り添いの時間に充てることができると思うがどうか
𠮷安)(3)中学校部活動の地域移行によって、部活動を受け持っていた教職員は、放課後に時間ができると考えます。不登校傾向のある児童生徒への寄り添いの時間に充てることができると思いますが、御所見をお聞かせください。
答)中学校部活動の地域移行によって、部活動を受け持っていた教職員は放課後に時間ができる。不登校傾向のある児童生徒への寄り添いの時間に充てることができると思うがどうかとの御質問にお答えします。
各学校では、これまでも不登校傾向のある児童生徒に対して、丁寧な寄り添いの対応を行ってまいりました。担任をはじめ、学年主任、養護教諭、教育相談担当、生徒指導主任、管理職などが連携し、教職員による日常的な声かけや教育相談、生活ノートの活用、さらには電話連絡や家庭訪問などを通じて児童生徒との信頼関係を築き、早期の対応に努めております。
加えて、教室に入ることが難しい児童生徒に対しては、別室登校や放課後登校、ステップアップルームの活用、教育支援センターとの連携による個別支援など、状況に応じた柔軟な対応を行ってきたところでございます。
中学校部活動の地域移行後も学校全体で児童生徒を支える体制を維持しながら、これからもきめ細かな支援の充実に努めてまいります。
𠮷安)ありがとうございます。
確かにおっしゃられたように、部活動の担任もされながら、受け持ちもされながら、今でもそうやって寄り添っていただいていることは重々承知しております。
そもそもですが、部活動の地域移行は教員の働き方改革の要素もあるため、制度では放課後の時間を空ける仕組みだとは思いますので、この提案はいささか矛盾を感じております。
令和4年度時点で、先ほど言いました中学校生徒は174人おります。今よりさらに寄り添ってほしいというお願いとなります。矛盾点も踏まえていただいて、再度御見解をお聞かせください。
答)不登校または不登校傾向にある児童生徒への対応ということについては、個々によって状況がまちまちでございまして、なかなか対応が難しいところもございます。
ただ、子供たち、あるいは家庭のほうに寄り添って対応していくということは大切なことだろうと思いますので、これからもそれは続けてまいりたいと思います。
𠮷安)ありがとうございました。件名1の(1)(2)(3)を総括して、教育長へは最後の御質問となります。
湯野との市境から車で3分の山口市徳地の山あいに、風呂元さんという方が大人のひきこもり対策、就労及び社会復帰のためのアルカディアという施設があります。
心の病は脳の構造と摂取する食品と生活環境に原因があると研究されております。実際に、ここの施設では10年を超える長年ひきこもりであった青年が、数人ですが社会復帰されております。そんな施設が、この周南市の近くにあることをより多くの方に知っていただきたいです。
大人のひきこもりに関するデータを見せていただきました。当事者の方の大半が、子供の頃いじめを受けたことがある、もしくは不登校の経験があることが読み取れました。
内閣府の調査では、令和5年度で大人のひきこもりは全国で約146万人とされております。これは風呂元さんの持論ですが、この大きな数字のうち半分でも社会復帰することができれば、日本が今抱えている労働者不足問題を、少しかもしれませんが解決できるとの思いから、地道に活動されておられます。大人のひきこもりを解決するなら、事前の対策で学校教育でいじめ、不登校の対策を徹底的に行うことが大変重要であるとのことです。
私もこの考えには大いに共感いたします。不登校で悩む子供一人一人の人生がかかっています。子供もまたその保護者も学校も先生方も、ここまでしてくださったのならもう十分です。ありがとうございましたと保護者の方に言っていただくまで、徹底的にガチンコで当事者家族とぶつかり合い、学校教育で子供たちを誰一人取り残さないように救うんだという強い思いで取り組んでいただきたいと切に願います。
徹底的に寄り添うことと、大人のひきこもりにつながる児童生徒のひきこもりを未然に救うことについての2点を、教育長に最後の御見解をお聞かせください。よろしくお願いします。
答)子供たちには社会の中で自立して、他者と連携・協働しながら生涯にわたって生き抜く力、あるいは地域の課題解決を主体的に担うことができる力、こういったものを身につけていくことは、これまでの時代も、そしてこれからも求められているというふうに思っております。
そうした力を身につけるためには、各家庭における教育というのはもちろん大切ですけども、学校という場で同世代の仲間と過ごしながら、自分の考えを広げたり深めたり、さらには人として大切なことを学んだりするという経験を積むことで、自分の成長につなげていくということが必要だというふうに思っております。
また、地域の方々との交流を通して地域のことを考えたり、将来について考えたりするということも、子供たちの将来を生き抜く力を育むきっかけになるというふうに思います。
教育委員会では、先ほど答弁で申しましたけども、昨年度末に基本理念を未来を生き抜くこどものための興味・楽しさ・勇気を育むこどもまんなか教育とした第3期教育大綱を策定しました。
この基本理念の具現化に向けて、学校と家庭と地域が信頼のトライアングルを形成し、その真ん中に子供たちを置いて、それぞれがそれぞれの役割を果たしながら子供たちの成長に関わっていくということを目指してまいります。皆様の御理解と御協力を頂けたらありがたく思います。
𠮷安)ありがとうございました。今日ここで教育長が改めて言っていただいたことを、教育長からのトップダウンで教育関係者の方と再度共有していただけたらと思います。誰一人取り残さない教育を今後も引き続きよろしくお願いいたします。
誰一人取り残さないというのは捉え方にもよりますが、難しく繊細な方針のように考えますので、引き続き、こどもまんなか宣言に関する子供支援策、例えば学校付近の横断歩道のカラー化などの事業拡充をぜひよろしくお願いします。次に移ります。
2.市民館跡地の利活用について
- 国の機関集約化について、進捗状況は。
𠮷安)市民の方は御存じの方も御存じではない方もおられますので、今回改めて取り上げさせていただきました。市役所の道路を挟んだ東向かいに旧市民館がありました。ここは、今市役所臨時駐車場となっております。この跡地に国の集約機関施設が建設予定です。入る機関は、周陽の法務局、今宿の税務署、住吉町のハローワーク、桜馬場の自衛隊周南地域事務所、速玉町の労働基準監督署の5つでございます。市役所隣に、市内中心部に集約すると確かに便利になると思います。車であちこち行かなくても、ここで完結することが増えると思います。
私は、周南市市民館跡地の施設建設計画に関する調査特別委員会が発足されて昨年12月に閉じられるまで委員でしたので、議論もさせていただき、聞かせていただき、それを市民の皆様にお知らせしてきたつもりです。
ですが、「今の場所でええんじゃないんか。」とか、「集めたら今よりその辺が渋滞したりやせんか。」とか、「また市内に箱物建てるんか。」とか、でも逆に、「そりゃええことじゃね。」と、「便利になるね。」という声もあります。様々です。
ただ、皆様に共通して心配されるのが駐車場問題です。今までの報告では、検察庁側の現在85台停めれる臨時駐車場の上に施設ができる予定だと思います。国の庁舎で働かれる人の分、利用される方の分、そしてなくなった85台分。今でも本庁舎前駐車場147台が平日の10時を回ったあたりから満車になる日がたまにあり、この場合は臨時駐車場とその南側にある保健センター駐車場38台を利用されています。
新年度のスタートや何かしらの要因がある日は全ての駐車場が満車となり、本庁舎駐車場入り口の東側、西側とも満車が解消されるまで待つ車で列ができております。それを踏まえて、庁舎の裏に当たる児玉公園側に立体駐車場の計画もあるかと思います。
現保健センターを解体して、文化小ホールと保健センター機能併設の計画もあると思います。小ホールは市長が公約に掲げられ、多くの市民の方からの要望もございます。当初はあくまでもそれらが臨時駐車場と保健センター駐車場を含む部分での計画でした。大変手狭なスペースに収まるのかと疑問を感じておりましたが、昨年度、山口銀行徳山支店が施設建て替えに伴い、そこも含めた敷地全体で考え直すとの話になり、面積も増えたし、かなり余裕ができた計画に変わったと認識しております。
ただ、山銀さん角の県道沿いの交番の土地取得は交渉中だと記憶しております。今申し上げたことを踏まえて御質問いたします。
(1)国の機関集約化について、現在の進捗状況はをお聞かせください。
答)国の機関集約化についての御質問にお答えいたします。
これまで、国の機関の集約化につきましては、平成27年に設立された国及び市の所有財産の有効活用等を検討する、国・周南市有財産の最適利用推進連絡会において協議を重ねてまいりました。
その中で、老朽化が進む施設への対応や利用者の利便性の向上を図るため、市民館跡地に税務署やハローワークなど市内に点在する国の機関を集約した庁舎の整備を検討してきたところです。
国の庁舎整備事業につきましては、毎年夏頃、学識経験者等で構成される事業評価小委員会による評価を経ます。そして、事業の採択が行われた場合、予算措置が講じられ事業化される運びとなります。
現在、早期の事業採択に向けて国と協議・調整を進めているところであり、現時点でお示しできるものはございませんが、御報告できる状況になりましたら、市民や議会の皆様へ速やかにお知らせさせていただきます。
𠮷安)ありがとうございます。立体駐車場は何台を想定されておりますでしょうか、お聞かせください。
答)現在、まだ基本計画等の中間報告の段階でございますけども、そこまでに検討したところでございますが、各施設のピーク時における最大値を想定いたしまして、必要台数を230台から320台程度と試算しているところでございます。
𠮷安)ありがとうございます。この計画は10年前からの計画だとお聞きしました。御答弁を聞いた上での質問ですが、集約機関についてはもう決定事項という認識でよろしいでしょうか。
市民の方が幾ら必要ないと言われても、庁舎は国の施設でありますので、市議会で建設に対しての議案が上がり、各議員に賛否を問うわけでもなく、建設することが前提の下、国との調整が進んでいるという認識で合っているかを確認させてください。
答)この国の機関を今分散しているところを市民館跡地に集約するというところは、この町にとって必要な事業だろうというふうな形で我々のほう考えております。
現在、国との協議の中では、議員が先ほどお示しいたしました法務局、税務署、労働基準監督署、ハローワーク、そして自衛隊の事務所と、この5つを入れるということで今、協議をしているところでございまして、この形で国のほうも、今、小委員会のほうに、事業評価のほうに出すというふうな形で今進めております。
𠮷安)庁舎の建設費は全額国の負担であるのか。集約される予定の既存の5施設のその後の土地はどこに帰属するのか。建物は有効利用して残すのか。また、解体するのであれば、解体費用は市と国とどちらの負担になるのか。庁舎建設に伴う立体駐車場建設の負担割合の5点をお聞かせください。
答)まず、国の庁舎の負担でございますけども、今回、国の庁舎につきましては、全て国の施設が入るということで今考えておりますので、全て国の負担というか、国が全て事業費を出すという形になります。市のほうはそこについては支出のほうはございません。
次に、土地でございますけども、これは今集約してくる土地全てが市のものになるとかという話ではなくて、今、市民館跡地のところに国の用地がございます。その国の用地の評価と同じ額、等価交換と申しますか、そういった部分の土地部分を市のほうが取得してくるという形になりますので、市内に点在する国の土地との交換になります。
ですので、国が持っている部分、持ち続けている部分、市が新たに取得する部分というのが、その2種類生じてくるというふうに認識していただければよろしいかと思います。
そして、庁舎の活用でございますけども、国が所有したままの部分につきましては、国が活用方法のほうは考えるという形になります。市と交換する部分につきましては、活用できるものは、それは活用していきたいというふうにも考えています。
また、活用できないものは、これは次の4番目の質問になるかと思いますけども、解体をしていただくようにはなると思います。その解体費につきましては、原則、国のほうが負担をするという形で、市といたしましては、更地でそこを取得したいというふうに考えております。
そして、最後は立体駐車場でございますけれども、これにつきましては、それぞれの負担、今後は議員おっしゃいますように山口銀行も入ってくるかと思います。そういった形で、それぞれが使った部分は負担できるような形で、今、協議のほうを進めているところでございます。
𠮷安)詳細をありがとうございました。次に移ります。
- 文化会館の大規模改修を受けて、文化小ホールの建設は一旦見直すべきではないか
𠮷安)(2)文化会館の大規模改修を受けて、文化小ホールの建設は一旦見直すべきではないかについてです。
文化会館は、昨年度、築42年が経過し(昭和57年建設)、天井が落下するおそれがあることの対策工事、受電盤の取替え、アスベスト撤去、誘導灯更新、舞台等更新、トイレ改修、座席シートの交換などを含め、現段階の試算で63億円の大型公共補修工事となります。
文化会館は全国に誇れる音響環境を有しており、数多くの有名アーティストが絶賛することで知られており、本市には欠かせない大型公共施設であるとの認識は誰しも共通であると思います。
ただ、一つ懸念されることがあります。令和9年度2月から閉館して、そこから工事が始まり、修繕完了予定が令和10年10月予定であります。かなり先の話であり、近年の急激な物価高、人件費の高騰の先行きが見込めません。63億円で済めば一番いいと思います。いざ終わる頃になると、あまり考えたくはありませんが、70億円、80億円にならなければいいなと。
実際に須々万に令和8年度3月完成予定の北部交流拠点施設は、基本計画時約10億円でありましたが、約4年たち、結果的に積算金額は約1.5倍の約16億円になってしまうのが今の建設現場の実態です。
積算価格も、ウッドショックやコロナ前は1年間ぐらいはまず安定していました。近年の激変は誰にも予想がつかないと思います。であるからこそ、文化小ホールが絶対に必要ないとは思いません。需要があるのは事実ですが、本市が文化芸術における予算は底なしではなく、一定のものがあると考えるからこその思いからの質問です。御見解をお聞かせください。
答)文化小ホールの建設についての御質問にお答えいたします。
文化会館の大規模改修につきましては、調査の結果、万一の場合、人命や事業継続に多大な影響を及ぼす可能性があり、緊急性の高い改修であると判断されたことから、優先的に実施するものであります。
一方で、文化小ホールは、市民が幸せを感じながら生活を営む上で必要な文化や知の力の拠点となる施設として検討を進めているところです。
また、第3次周南市まちづくり総合計画に掲げるまちの強み進化戦略を具現化する上で、文化会館とは異なる役割を担う重要な拠点施設としても位置づけております。
現在検討を進めております市民館跡地の利活用に向けた取組は、現世代はもとより、将来世代にわたって、より多くの市民の皆様の幸せを実現し、町の魅力や都市力の向上を図る上でも、本市にとって必要であると認識しております。
私は、これを町の価値を高める未来を見据えた投資だと考えております。
こうしたことから、文化会館の大規模改修があるという理由だけで文化小ホールの建設を見直すのではなく、今後も市民や議会の皆様、関係者の方々とも意見を交わしながら、財政状況や事業の優先順位なども総合的に勘案し、文化小ホールを含めた市民館跡地の利活用について、引き続き検討を進めてまいります。
𠮷安)ありがとうございました。先ほど私が申し上げた、金額が最終的に跳ね上がる可能性についての懸念についての御見解をお聞かせください。
答)現在、文化会館の大規模改修のスケジュールといたしましては、昨年の8月8日の市議会全員協議会のほうで御説明しております。
そのときには、今、議員もおっしゃいました、今予定をしておりますのは、適合化改修であったり保全改修、防災改修、あと改善改修と、これら4点の項目から優先度をつけながら計画を図っておるところでございます。
予定としましては約63億円というところを出しておりますけれども、現在基本設計を進めております。今年の9月末には終了予定とし、引き続き10月から来年の5月までは今度は実施設計をする予定としております。工期につきましては、令和9年の2月から21か月をかけて、令和10年10月までを予定しておるところでございます。
この概算見込みにつきましては、まだ基本設計、実施設計等が完了しておりませんので、現時点では、想定は今お答えすることができません。当然、しかしながら、物価高騰という影響もあることから、今の基本設計、実施設計の中で改善できるものは改善し、必要最低限になるべく持っていきたいというふうに考えております。
以上です。
𠮷安)ありがとうございます。残り時間が少なくなってしまい、すみません。
保健センターは解体ありきなのでしょうか。令和元年度と令和2年度に2年間で約5,000万円をかけて外壁改修工事、屋上防水工事、エアコン工事などしたばかりでございます。長寿命化工事をすれば、まだあと20年ぐらいはもつのではないでしょうか。まだ築34年だったとお聞きしております。山銀さんまでの土地を含めてお考えであるのであれば、既存の保健センターは残すということは検討していただけないでしょうか、お聞かせください。
答)保健センターにつきましては、現在、国の集約化であったり文化小ホールの建設、駐車場の整備だと、山口銀行とのどのような形になるか、そういったまだ一体的な利活用の中でその形がどうなるかというのを、市民の利便性の向上がどのような形で図れるのか、そういったところをしっかり検討しながら、その方向性についてはお示ししたいというふうに考えております。
𠮷安)無駄な箱物なら必要ないというのが今の世論だと思います。
ただ、やはり公共施設というのは地域にとって必ず必要です。当然新しく建てるのであれば、解体工事から始まり基礎工事、建物、設備、器具、メンテナンスと幅広い分野への業種の地元経済への影響、建設業に従事される方の雇用の確保及び技術の伝承の意味合いもあると思います。
日頃の会議はもちろんのこと、5月は各団体の総会の時期でございました。何度各地区の市民センターや会館、ホールの会議室などの本市の公共施設を利用させていただいたか分かりません。公共施設でないものも含めますと、昔でいう公民館、自治会館、市民センター、各支所がその地域にあることがどれだけ大切かを身をもって分かりました。それを踏まえての再質問です。
建設予定の300席から500席の小ホールは、他市の同等の規模のホールの建設費を調べましたところ、およそ15年前から20年前の金額にはなりますが、二、三十億円かかっておりました。それを今の金額に換算すると、およそ倍の40億円程度になるかもしれないと推測いたします。
建て替えの必要性が出ている市民センターが各地区にあると思います。仮に40億円あれば、市民センターを建設する費用に優先的に回すというお考えはございますでしょうか、お聞かせください。
答)当然、市民センターをはじめとする公共施設の整備につきましては、まちづくり総合計画であったり、公共施設再配置計画に基づいて、各施設の役割や必要性を整理して優先順位をつけていきたいと進めておるところでございます。
文化小ホールにつきましても、その意義や役割を踏まえつつ、全体のバランスを考慮し、財政状況であったり、事業の優先度を勘案しながら検討する必要があるというふうには考えております。
市の施設の整備につきまして、実施する順番等々でございますけれども、本市のまちづくりの方針を踏まえながら、限られた財源の中で事業効果であったり緊急性、持続可能性等を総合的に勘案して優先順位をつけて、そして進めてまいりたいというふうに考えております。
𠮷安)ありがとうございました。
いろいろと質問を重ねましたが、どれもお一つお一つ丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。1、2件ともに併せてですが、今後、公共施設再配置計画、子供支援のための予算の拡充のことも全体で考えてみていただければありがたいです。
以上で、一般質問を終わります。ありがとうございました。